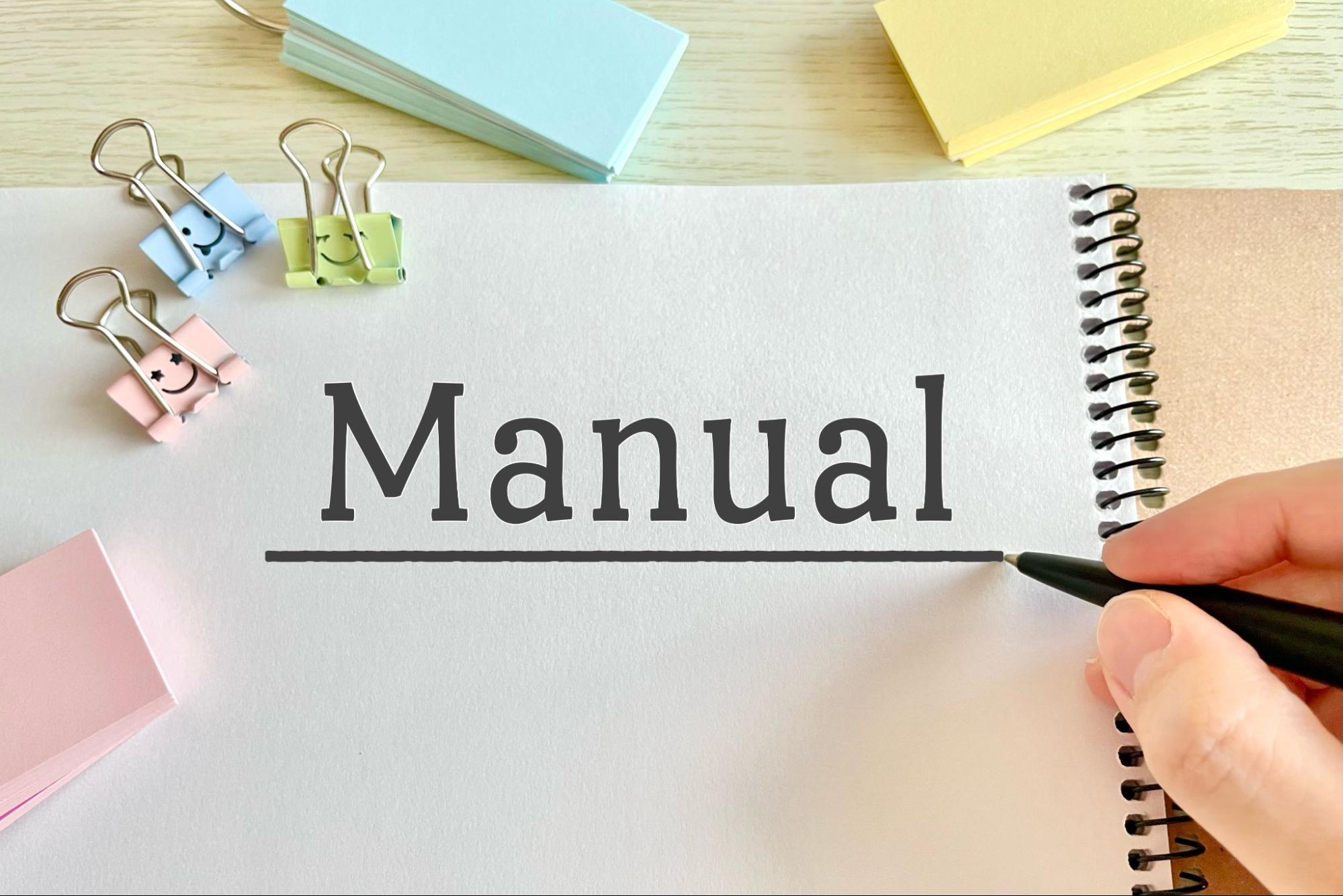クオリティの高い翻訳をおこなうときに欠かせない「スタイルガイド」。
スタイルガイドとは一言でいえば翻訳をする際の「決まりごと」です。
特に、多くの翻訳者が関わるような大規模な翻訳などの場合、この「決まりごと」にひとりひとりのブレがあると、その修正にも時間が必要となり、品質の低下や時間のロスに繋がってしまいます。
スタイルガイドで決まりを最初に作っておくことで、翻訳のクオリティを高く維持することができるでしょう。
本稿では和訳のスタイルガイドとはどのようなものかを解説し、スタイルガイドに含まれる項目についてそれぞれ説明します。
スタイルガイドとは?
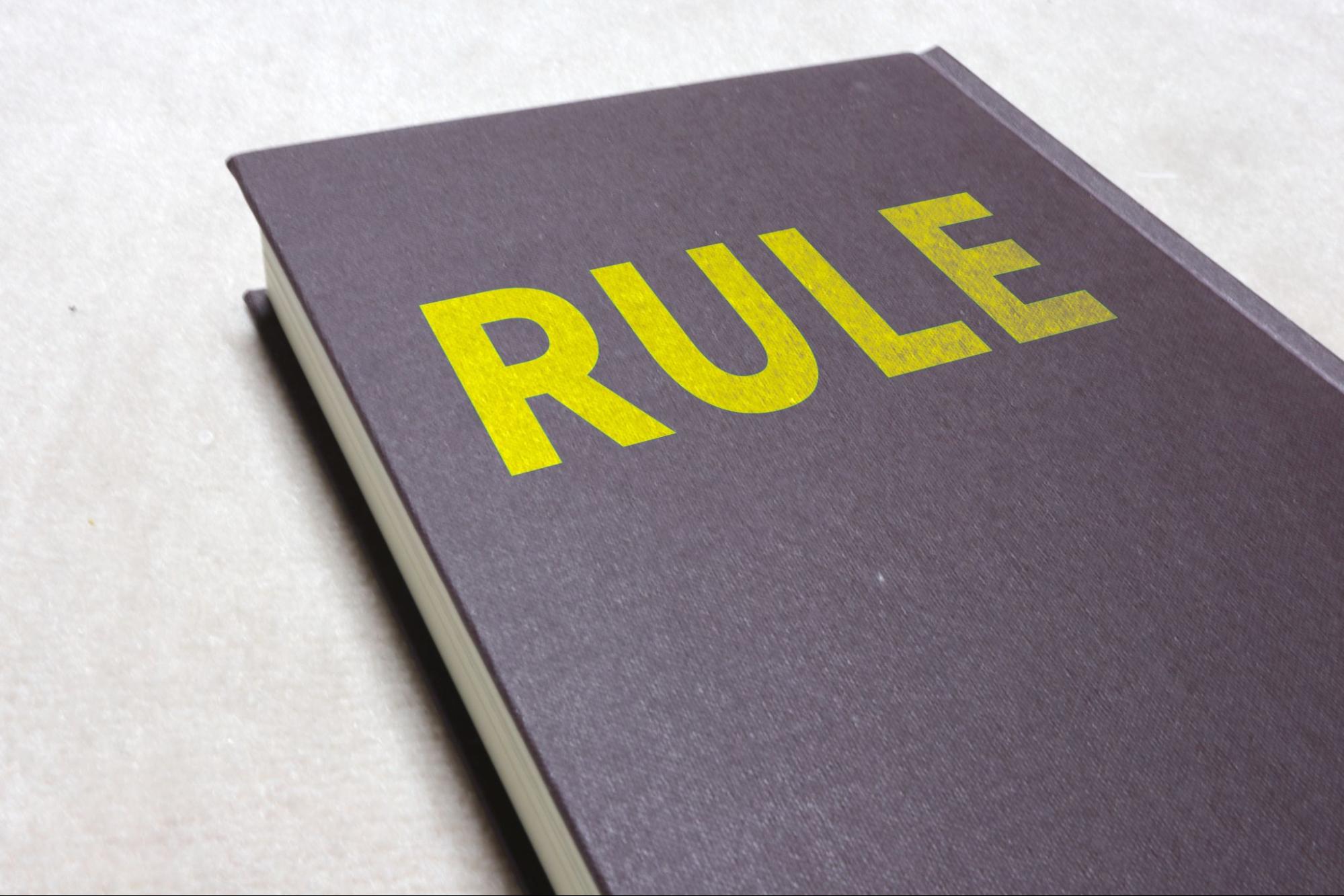
「スタイルガイド」とは先ほども述べたように、翻訳をおこなう際の「決まりごと」をまとめた文書のことです。
特に翻訳者が複数人いる場合や、ボリュームの大きい案件、将来的に継続する案件の場合などにはあらかじめスタイルガイドを作成しておくことが必要となります。
目的
スタイルガイドを使用する目的は以下3点などが挙げられます。
- 複数の翻訳者が翻訳を担当するため
- 表現のばらつきを防ぎ、翻訳のクオリティを一定のものにするため
- クライアントの希望に沿った翻訳にするため
スタイルガイドがあることで、翻訳に関わる人員に変化があってもクオリティの高い、一定の翻訳が可能となります。
スタイルガイドは誰が準備する?
スタイルガイドは基本的にクライアント側が準備します。
翻訳に必要な資料としてあらかじめ提出されていれば、翻訳者(翻訳会社)がその都度確認する必要もなく、クライアントの要望に応じた翻訳の作成が可能となります。
特に指定がされていなかった場合には、要望通りの翻訳をするためにクライアントと翻訳者(翻訳会社)間で最初にすり合わせをおこない、必要な項目を満たすスタイルガイドを作成することになります。
スタイルガイドの主な項目

スタイルガイドの中の主な項目について見ていきましょう。
業界が違っても、基本的なルールの項目は同じです。
ただし、専門的な用語などについては一般的なルールとは異なり、業界ならではのルールが存在する場合もあるため、クライアントの要望に合ったスタイルガイドの作成が必要です。
文体
文体とは文章のスタイルのことを指します。
文体は翻訳の際には必ず統一しておく必要があります。
日本語訳でいうところの「です・ます調」か「だ・である調」のどちらかに統一をするということです。
文体については、どの言語に翻訳する場合でも、最初に文語か、口語かを決めて置く必要があります。
文字
より読みやすく、わかりやすい文章にするために一部の漢字をあえてひらがなで表記することがあります。
例:子供→子ども
基本的には「常用漢字表」の漢字のみ使用することが多いですが、分野や業界によって普段使われている言葉が異なるため、確認し、共有しておくことが必要です。
文字の使い方についてはクライアントによってルールが異なります。
また、アルファベットや数字を半角にするか、全角にするかについても文字の部分で取り決めておく必要があります。
用語
同じ意味の複数の用語がある場合には、どちらを使うかをあらかじめ決めておき、表記にゆれが生じないように気を付ける必要があります。
同じ意味なのに複数の用語が同じ文章内で使われると、一緒のものを指しているのかがわかりにくく、読み手の混乱を招く可能性があるので注意しましょう。
また、日本語の場合は送り仮名に違いが発生することもあるので、読みやすい訳文に仕上げるためにも送り仮名は統一しておく方がよいでしょう。
スペース
文章の可読性を上げるために重要な役割を担うのがスペースです。
日本語の文章だと、スペースがなくても意味が通じますが、英文やカタカナが連続する場合には、スペースがなくては意味の通じない文章になってしまいます。
そのため、以下2点など、スペースに関してもルール設定が必要です。
- 英文や英単語を流用する際に、直前直後の日本語文章との間に半角スペースを設ける
- カタカナ複合語の間には中黒(・)または半角スペースを入れる
記号
括弧、句読点、疑問符、感嘆符、ハイフン、コロンなどのあらゆる記号についても、使用する文字と同様にスタイルガイド内で取り決めておく必要があります。
- 感嘆符や疑問符を訳文中でも使ってもよいかどうか
- 英文に使われる引用符を日本語訳にした場合には括弧に変換するのか、そのまま引用符にしておくのか
- 記号は半角表記にするのか、全角表記にするのか
違和感なく読みやすい文章に仕上げるためには表記の仕方をあらかじめ指定しておきましょう。
単位
単位の表現の仕方は日本語の場合アルファベット表記とカタカナ表記があります。
例:mm/ミリメートル
単位の表記についても文章の中では統一をし、アルファベットかカタカナかいずれかに合わせておくことが基本的なルールとなります。
クライアント独自の表現
クライアント独自の表現として、専門的な分野についての独自ルールの取り決めが必要な場合もあります。
業界用語などを翻訳する場合には、どのような表記をするのかをしっかりと事前に翻訳者とクライアントとの間ですり合わせ、意思疎通をしておくのが好ましいでしょう。
また、翻訳する内容によって、カジュアルな文章にしたい、ビジネス用に堅い文章にしたいなどの要望がでてくることもあるので、全体的な文章の雰囲気などについても翻訳者(翻訳会社)とクライアントの間でしっかりと共有ができていることが必要です。
まとめ
スタイルガイドにはさまざまな項目があります。
文章の量が少ない場合や、翻訳者が少人数で済む場合などにはスタイルガイドをあまり細かく設定せずに翻訳されたり、上記項目の一部のみ指定をする場合もあります。
しかし、翻訳する文章の量が多かったり、翻訳者が多く存在する場合などにはスタイルガイドがより重要なものとなり、翻訳の品質やスピードに大きく関わってきます。
翻訳会社に依頼する場合には、事前に翻訳資料としてスタイルガイドを作成しておくことをおすすめします。
また、スタイルガイドの作り方がわからない場合や、作ってみたけれど必要な項目は満たしているのか不安に感じる場合には翻訳を開始する前の段階で翻訳会社とよく内容をすり合わせておきましょう。
事前に翻訳したい内容のイメージをしっかり伝えておくことで、作成後の修正も少なく、理想の翻訳が手に入りやすくなります。

翻訳監修
セス ジャレット:Seth Jarrett
カナダ出身。翻訳会社のアイ・ディー・エー株式会社に13年以上在籍。翻訳者のクオリティーチェックから英語のリライトまで幅広く対応。自らパンやスイーツをつくる料理人でもある。